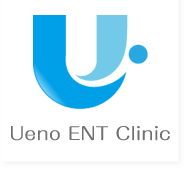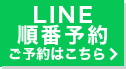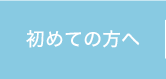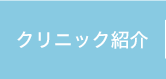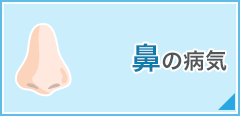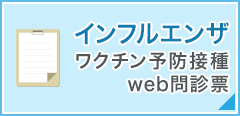その他について
味覚障害

味がまるでわからなくなったり、味覚が鈍磨したり、本来の味とは違った妙な味に感じたりする障害です。口の中が苦い、塩辛いなどと訴える自発性の異常味覚もあります。
高血圧薬、抗生物質ほか、各種薬剤の長期にわたる使用によって生じる薬剤性の味覚障害がよくみられます。
| 症状: | 甘味、酸味、塩味、苦味、旨味などの味覚が低下したり、何を食べてもまったく味を感じなくなったりすることもあります。また、口の中に何も無いのに塩味や苦味を感じたり、何を食べてもまずく感じられたりすることもあります。 |
| 検査: | 症状に応じて、味覚検査や血液検査などが行われます。 |
| 治療: | 薬剤が原因で味覚障害が起こっているような場合には、医師に相談のうえ、服用の中止または副作用の無い薬剤への変更をしてもらいます。血液中の亜鉛の不足により、舌の表面にある味を感じる細胞(味蕾)の新陳代謝が十分に行われなくなるために起こることもしばしばですが、その場合は亜鉛を補給する治療を行います。舌にカビが生えていて、痛みを伴ったりする味覚障害も稀に見られますが、そうした場合は、カビを除去する治療を行います。 |
気管支喘息
空気の通り道である気管支が慢性的な炎症を起こして狭くなり、ダニや埃、タバコの煙、ストレスなどの刺激によってさらに空気が通りにくくなって息が苦しくなる状態を喘息発作と言います。この喘息発作を繰り返し起こす疾患が気管支喘息です。
この状態は、アレルギーによる炎症が多く、特に小児では気管支粘膜が未熟なため、アレルギー反応を起こしやすくなります。
気管支喘息は小児の約6%、成人の約3%に認められ、その数は増える傾向にあります。家屋構造の変化によるアレルゲンの増加、大気汚染、食品や住宅建材などの化学物質、ストレスの増大などが、その要因と考えられています。
| 症状: | 「ゼーゼー」「ヒューヒュー」という呼吸音(喘鳴)、息苦しさ、激しい咳込み、胸の痛みなどが主な症状です。夜間や早朝に発作が起こりやすいのも大きな特徴です。気管支拡張薬を吸入すると、症状が楽になります。 |
| 検査: | 呼吸機能検査、気道過敏性試験、血液検査、皮内アレルギーテスト、痰の細菌検査、また必要に応じて胸部X線検査などが行われます。 |
| 治療: | 発作の治療と発作を起こさせないための気道炎症の治療が中心です。気管支喘息は慢性疾患であり、継続的な治療が必要になりますが、きちんと診療を続け、自己判断で治療を中断しないようにすることが肝心です。 |
発作が起こった際は、ステロイド吸入薬、気管支拡張薬などの薬物療法で炎症を抑えていきます。一方では、予防のために自宅からアレルゲンの原因となる埃・ダニ・タバコの煙などを取り除いて環境を整え(周囲の人の禁煙も必要になります)、規則正しい生活を心がけることなども大切です。
咳喘息
咳喘息は、慢性的に咳が続く気管支の病気です。一般的な喘息と同様、気道(呼吸をする際の空気の通り道)が狭くなり、冷たい空気やタバコの煙、運動、アルコール、ストレス、ハウスダスト(埃やダニなど)などの様々な刺激に対して過敏になっており、炎症や咳発作が起こります。咳喘息は気管支喘息とは区別されますが、その前段階と考えられています。
咳喘息は、アレルギー素因のある人に多いと言われます。アレルギー反応によって、気道が炎症を起こしてしまうせいです。
風邪に併発して起こることが多いのも特徴で、風邪をひいた後にいつまでも咳が残るようなら、この病気の可能性があります。
| 症状: | 8週間以上、慢性的で痰を伴わない乾いた咳が続きます(慢性咳嗽)。ひどい場合は咳が1年以上続くこともあります。ただし、主な症状が咳であり、気管支喘息に見られるようなゼーゼー、ヒューヒューといった喘鳴や呼吸困難はみられません。また、発熱や痰などの症状もほとんど出ません。夜中から明け方に激しい咳が出たり、寒暖差や喫煙で咳が出やすくなったりするのが特徴です。気管支喘息にも用いられる気管支拡張薬を吸入すると、症状が楽になります。 |
| 検査: | 胸部X線検査、肺機能検査、血液検査などを行い、丁寧に問診・診察をしたうえで診断をつけます。 |
| 治療: | 気管支喘息の治療に共通しており、気管支の炎症を抑えるために、吸入ステロイド薬や気管支拡張薬などによる薬物治療が行われます。適切な治療を受けなかったり、治療を中断したりすると、再発を繰り返したり、気管支喘息に移行したりすることもあります(咳喘息を放置すると、その約3割が気管支喘息に移行すると言われます)。難治化する前に耳鼻咽喉科などを受診し、きちんと治療を受けましょう。 |
上気道炎
上気道(鼻や喉)に様々な病原体が感染して症状を起こした状態を総称して上気道炎と言います。病原体の80~90%が、ライノウイルスやコロナウイルス、RSウイルスなどのウイルスです。
| 症状: | くしゃみ、鼻水、鼻づまり、喉の痛み、咳、痰、発熱、頭痛ほか、嘔吐、腹痛、下痢などの消化器症状がみられることもあります。 |
| 検査: | 多くは医師の診察によって診断しますが、ケースによっては血液検査や細菌検査などが行われます。 |
| 治療: | 細菌が原因の場合や、細菌感染を続発する恐れのある場合は、抗生物質を使用することがありますが、通常は水分補給と安静のみで10~14日以内に自然に治ります。 |
外来感染対策向上加算について
外来において受診歴の有無に関わらず患者の受け入れを行います。
当院では下記の院内感染防止対策に取り組んでいます。
- 院内感染管理者(院長)を配置し、職員一同で院内感染対策に取り組んでいます。
- 感染防止対策業務指針及び手順書を作成し、職員全員がそれに従い院内感染対策に取り組んでいます。
- 職員全員に対し年2回院内研修を実施し、感染防止に対する知識向上に取り組んでいます。
- 感染性の高い疾患(インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など)が疑われる場合は、一般診療の方と導線を分けた診療スペースを確保して対応します。
- 提携病院又は医師会と感染対策連携を取っております。
医院概要
| 医院名 | 上野耳鼻咽喉科クリニック |
| 診療科目: | 耳鼻咽喉科・内科 |
| 住所: | 〒110-0005 東京都台東区上野6-16-19 新丸屋ビル4F |
| TEL: | 03-3834-2822 |
| アクセス: | JR線「上野駅」広小路口 徒歩3分 東京メトロ日比谷線、銀座線 4番出口徒歩1分 |
診療時間
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00~ 13:30 |
○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
| 15:00~ 19:00 |
○ | ○ | - | ○ | ○ | - | - |
休診日:水曜日・土曜日・日曜日・祝日